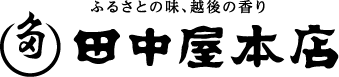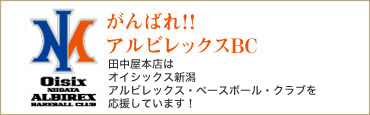笹だんご物語
六、郷土料理としての笹だんご
笹だんごの中に餡を詰めるようになったのは、砂糖が庶民の手に入るようになった明治の中期以降といわれます。それまでは、中に何も詰めないままで作られた「男だんご」であったり、あり合わせの惣菜を詰めて作られてきました。 言い伝えられてきたものだけでも、「味噌だんご」「ごまだんご」「くるみだんご」「あらめだんご」「きんぴらだんご」「ひじきだんご」など様々な「笹だんご」があるようです。要するに、だんごの中に入れられるものは何でも入れたのであり、それが「おやつ」やちょっとした腹ふさぎの料理となりました。作り置きしておいて保存性がある。しかも粉食なのでちょっとした時に食べやすい。まさに便利な間食として日常のケの日になくてはならないものだったのでしょう。
これに対して、ハレの日の笹だんごはやはり端午の節句、そして田植えが終わったころ笹の葉の緑も鮮やかになってくる季節のものです。ヨモギの香りも新鮮で、田植えの疲れも忘れてしまうほど、一年中で一番楽しい夏の喜びを告げる先触れの味です。この笹だんごはその家で一番良い米を使いできる限り沢山作りました。同じように作っていても家によって味は微妙に異なり、まして中身の餡やお惣菜の味は各戸の腕の見せ所。家々に明るい声が響き、笹だんごの味を競い合うのです。
街場の家も、親戚の農家からお裾分けの米や米粉を使って笹だんごは作られました。何がなくとも米はあり、その加工品としての笹だんごは貴重なおやつとなったことは街内もまったく同じです。特に初夏を彩る蒲原祭りの時節柄、五穀豊穣を祈る神事にはなくてはならない笹だんご。まさに新潟の味そのものです。
転載、複製、改変等を禁止します。